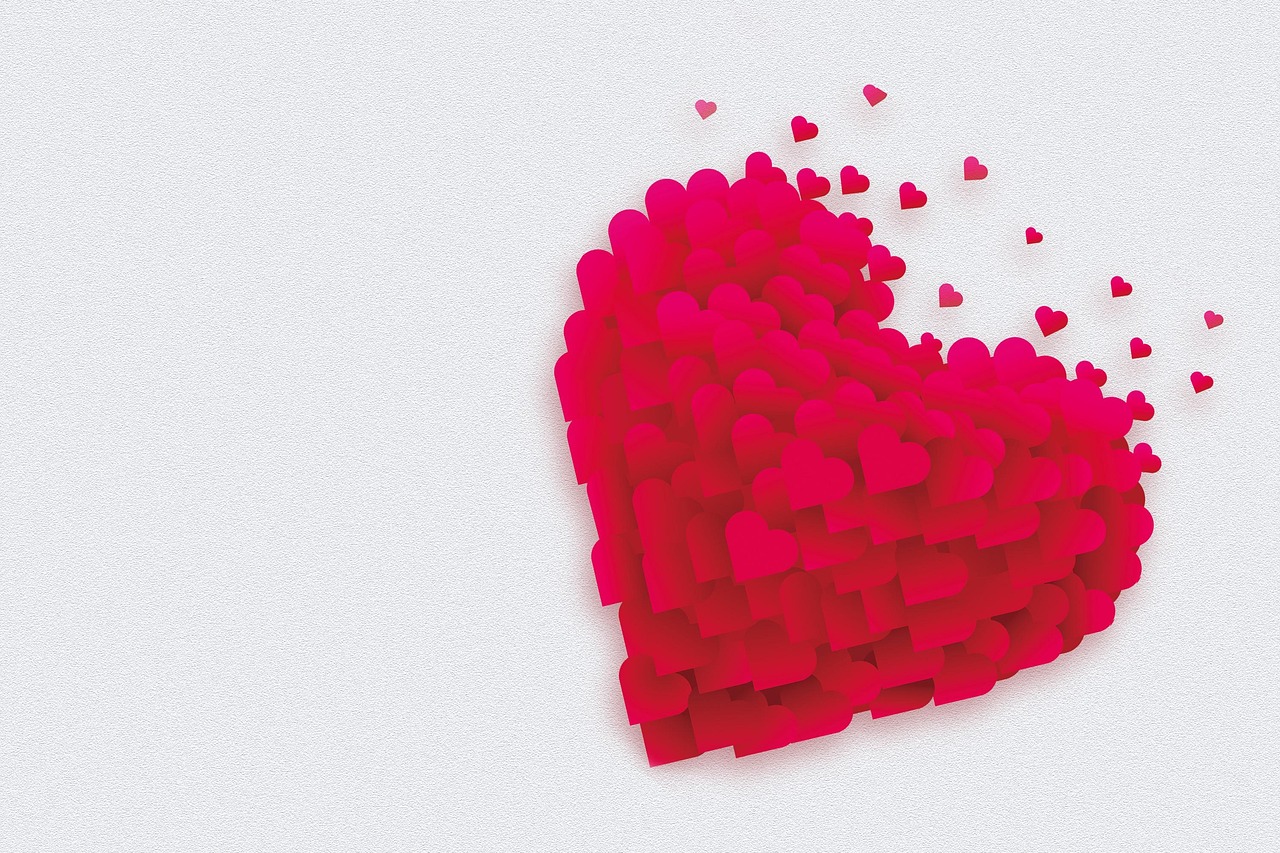血液内科ってどんな診療科なんだろう?
そんな印象を持たれる方が多いと思います。
自分の両親でさえ、どんな病気を診てるんだ?って言うぐらいなので。
この記事では、血液疾患の概要について解説します。
血液内科の奥深い世界 – 貧血から白血病まで、全身を支える血液の専門家
血液内科が扱う主な疾患 – 貧血だけじゃない、多岐にわたる疾患
血液内科と聞くと、「貧血」をまず思い浮かべるかもしれません。
溶血性貧血や巨赤芽球性貧血などは代表的な血液疾患です。
しかし、血液内科が扱う疾患は貧血だけではありません。
基本的には、白血球系疾患、赤血球系疾患、血栓止血系疾患に分かれます。
また、腫瘍性疾患と非腫瘍性疾患に大別されます。
具体的には、以下のような疾患が挙げられます。
- 血液悪性腫瘍(血液がん):白血病(急性骨髄性白血病、急性リンパ性白血病、慢性骨髄性白血病、
慢性リンパ性白血病)、骨髄異形成症候群、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫など - 赤血球系疾患:溶血性貧血、巨赤芽球性貧血、再生不良性貧血、サラセミア、鉄欠乏性貧血など
- 出血性疾患:血友病、血栓性血小板減少性紫斑病、免疫性血小板減少症、von Willebrand病など
血液内科が扱う疾患は、良性のものから悪性のものまで、非常に多岐にわたります。
血液疾患の診断と治療
血液疾患の診断には、血液検査が不可欠です。
血液細胞の数だけでなく、顕微鏡で血球形態を確認したり、血球機能を調べます。
また、疾患によっては骨髄検査(骨髄穿刺・骨髄生検)を行い、血液細胞が作られる骨髄の状態を評価し、
正確な診断につなげます。
さらに遺伝子検査や染色体検査を行い、疾患の原因や特性を把握します。
治療方法は疾患の種類や進行度、患者さんの状態(PS:Performance Status)や認知機能に合わせて、選択します。
基本的にはガイドラインに準じた治療を行いますが、ある意味オーダーメイドな治療になります。
抗がん剤による化学療法、免疫抑制療法、輸血などの支持療法、放射線療法、造血幹細胞移植など、
様々な治療方法を組み合わせ、患者さんにとって最適な治療を提供します。
血液内科医の役割 – 患者さんと共に歩む専門家
血液内科医は、単に血液疾患を診断し、治療するだけではありません。
血液疾患の治療は、治療期間が長期間、場合によっては10年以上にわたることも少なくありません。
患者さんやそのご家族と長期わたり向き合い、精神的なサポートを行うことも重要な役割です。
患者さんの不安や苦痛に寄り添い、共に病と闘っていく姿勢が求められます。
最後に
血液は生きるために不可欠なものです。
血液に異常が生じると、様々な症状が現れます。
血液内科は、そんな血液疾患を専門とし、患者さんが安心して日常生活を送れるように診断から治療まで行います。
もし、健康診断などで血液検査の異常を指摘されたり、原因不明の貧血や出血、発熱などが続く場合は、
血液内科を受診してみてください。
専門医があなたのために力を尽くしてくれるはずです。